「頼れる感覚の再定義」?!
以前動きのプロセスについての記事を書いた事がありました(こちらの記事)この中で、「感覚は動きの結果」という事を書きました。今回は、この感覚というものについて、もう一度考えてみました
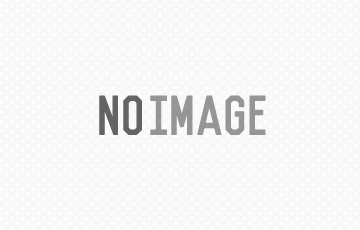 過去記事一覧
過去記事一覧
以前動きのプロセスについての記事を書いた事がありました(こちらの記事)この中で、「感覚は動きの結果」という事を書きました。今回は、この感覚というものについて、もう一度考えてみました
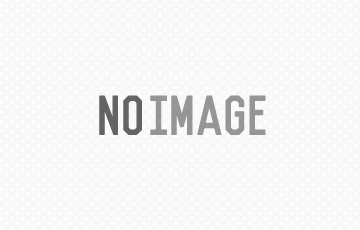 過去記事一覧
過去記事一覧
楽器ケースや荷物をしょって歩くときや、楽器を構えているとき。そういう時に、ひょっとしたら必要以上の力で動いているかもしれません。自分の身体に任せて、必要な力でやりたいことをやるにはどうするかを考えました。
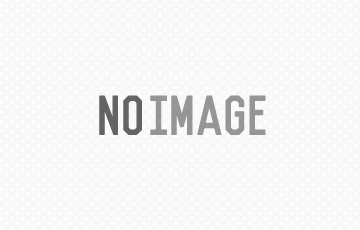 音楽・演奏について
音楽・演奏について
練習しているとき、いつの間にか「ここはこういう失敗をしそうだから、こう対処して演奏しよう」とか「こんな失敗をしても大丈夫なようにこういう方法を身に着ける練習をしよう」とか考えているときがありませんか?今回は、こういう練習…
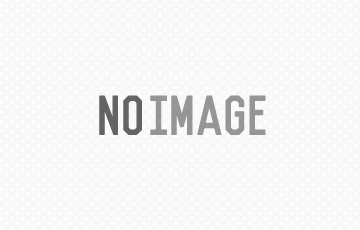 過去記事一覧
過去記事一覧
先週のBodyChanceでの授業と、自分の実践を含めて演奏における不安や、嫌な感覚についての向き合い方が変化できたので、どういうふうにそれらと向き合うか、それをここにまとめてみます。
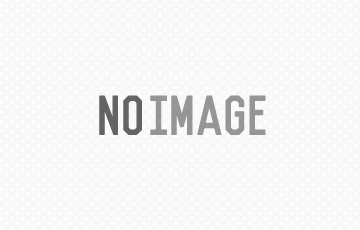 過去記事一覧
過去記事一覧
何かを選択したり、決断するときには、ある種の決意や勇気が必要になります。勇気は「勇気を絞り出す」という言葉がありますが、果たして勇気は自分の中から絞り出すことでしか生まれないのでしょうか? 今回は、中々決断が下せない時、…
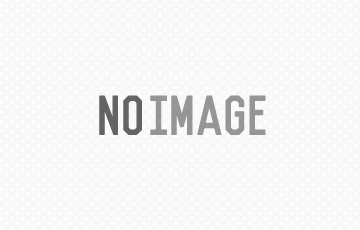 過去記事一覧
過去記事一覧
今回は何か失敗した時の反省のやり方を提案してみます。何かに失敗したとき、大抵は次に失敗しないように反省をすると思うのですが、皆さんの「反省の中身」はどういうものになっていますか?
 音楽・演奏について
音楽・演奏について
「会場に来てくれた人が、今日の演奏を楽しんでもらえると良いな…。」 「綺麗な音を聴いてもらおう」 「来てよかったと思ってもらえる演奏会にしよう。」 良い演奏をして、 充実感や満足感を得たい気持…
 「理想の未来」を手にするために
「理想の未来」を手にするために
「おめでとう」という言葉や、 「いい感じだね」・「素晴らしい!」など、 昔から 「ほめて伸ばす」 という言葉があるように、 ポジティブな言葉・ほめる言葉というのは、 人に自信をもたらしたり、 人を育てる力があります。 &…
 「自分の人生」を生きる
「自分の人生」を生きる
いま、自分の中に解決したい問題や達成したい目標があるとして、 何かのヒントを得ようと、 誰かの話を聞いたり、 ワークショップやグループレッスンに参加したりすると、 これまでは思い浮かばなかった新しいアイデアが生まれたり、…
 雑記帳・思う事
雑記帳・思う事
多くの場合、 人は、何かを失敗したら、 「どうして失敗したのか?」 原因を探ろうとするし、 「物事が思うように上手くいかない」と感じた時も、 何がブレーキをかけているのが? 原因を探ろうとします。 &nbs…